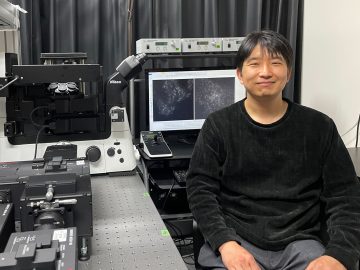
2025年4月1日付で生体機能解析学分野の准教授に着任いたしました柳川正隆と申します。
私は2006年に京都大学理学部を卒業後、同大学院理学研究科生物物理学教室に進学し、七田芳則教授の下で「代謝型グルタミン酸受容体の活性化機構」について研究を行いました。この間、日本学術振興会特別研究員(DC1)を経て、2011年に博士(理学)を取得しました。博士課程修了後も同研究室にて2013年まで「視物質ロドプシン類の熱活性化頻度の生化学的解析手法の開発」を行いました。2013年からは理化学研究所に基礎科学特別研究員として入所し、佐甲靖志主任研究員の下で「細胞内1分子動態計測に基づくGタンパク質共役型受容体 (GPCR)の薬効評価法の開発」に従事しました。同研究室には研究員、JSTさきがけ専任研究員を経て、現在も客員研究員として在籍しています。2023年からは、東北大学大学院薬学研究科の准教授として、井上飛鳥教授と共に「GPCRのシグナル伝達機構の空間的制御機構の解明」に取り組んできました。本学でも、飛鳥さん・スタッフ・学生のみなさんと連携し、「GPCRが司る細胞内シグナル伝達の分子レベルでの理解」を深めていきたい所存です。
GPCRをはじめとする膜受容体は、細胞表面からの情報入力を司るため、薬の標的として主要な位置を占めています。薬を受けたGPCRは多様なシグナル伝達分子を介して細胞内の複数の経路に情報を伝えます。また、近年の研究から、GPCRは薬のかたちに応じて情報伝達経路を調節できることも明らかになってきました。主作用となる経路をより選択的に調節できる薬は、既存薬がもつ副作用を低減する効果が見込まれます。このため、「GPCRが細胞内でどのようにして経路選択を実現しているのか」を理解することは、次世代薬の開発において重要な課題です。
私はこれまで、生きた細胞内で蛍光標識したGPCRとシグナル伝達分子を「4色同時に1分子レベルで観察する蛍光顕微鏡法」を開発してきました。薬刺激前後の分子のふるまいを観察すると、活性化したGPCRがシグナル伝達分子と50-200 nmの小さな「部屋」に集まる様子が見えてきます。薬の種類に応じてGPCRと一緒に「部屋」に入るパートナーが変わるため、経路選択にもこの「部屋」への出入りが重要な役割を担うと考えています。本学では、この「部屋」がどのようなメカニズムで形成され、どの程度情報伝達に重要かを定量的に明らかにしていきます。
京都大学への着任を機に、薬学部・薬学研究科における教育・人材育成を通じ、学生のみなさんと共に従来の薬理学の教科書の枠を超えて、薬の作用を情報科学の枠組みから捉えなおす方法を模索していきたい所存です。また、先端顕微鏡法に基づく未来の創薬基盤技術開発を産学連携により実現していきたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
